ホークス✕ベイスターズの三連戦を振り返る
6/13・14・15の金土日でペイペイドーム・ホークス✕ベイスターズの三連戦が行われました。
いやー、ベイファンとしてはなかなか厳しい結末となってしまいましたね。
ベイスターズの野球については前々から思っていたことがあり この3連戦でホークスの攻撃を見るにつれ、特にそう感じてしまった点があります。
ホークスにあって ベイスターズにないもののひとつ、 それは打撃における自己犠牲精神かなと。
ホークス以外でも他チームは自己犠牲精神に溢れたバッターが多いのかな〜と言う点です、まあチームがそうさせているのかなという部分もありますが。。
土曜日の2戦目の今宮選手などはランナーがセカンドの時など自分の打率降下を犠牲にしてでも叩きつけたセカンドゴロとか打ったりして(しかも2打席)、自分の成績よりチームの勝ちを重視した打撃が見られます。打率で3割近く、ホームラン14本などの成績をあげる今宮選手でもこんな打撃をしてくれるのです。
ホークスに限らず常勝を義務付けられているようなチームは こういった打撃をする選手が数多く見られます。
80年代中頃から90年代中頃にかけて西武ライオンズが黄金時代だった時にもこのようなバッターが多く見られました。
87年にライオンズがリーグ優勝した時、規定打席到達者においてのチーム内首位打者は石毛選手の2割6分9厘でした。これはチーム バッティングに徹した選手が多かったからもあるのではないかなという風に思っています。
当時の私は子供ながら、ライオンズは右打ちの上手い選手が多いな・・・という印象を持って見ていました。
そして清原選手が打撃のタイトルを取れなかったのは 常勝チーム においてのチームバッティングに徹したせいもあるのじゃないかと思っています。
【打撃のタイトルホルダーが毎年 恒常的に出るチームは優勝できない!?】
上記はかなり乱暴な極論ですが、翻って横浜は打撃のタイトルホルダーをコンスタントに排出しています。伝統的に、自由に打っていいと言われている打者が多いからではないかと思っています。
実際試合を見ていてもノーアウト3塁 あるいは1 アウト3塁で、味方のリリーフの状態から言って「ここで1点を取ればほぼほぼ勝てる」という場面でもホームランかヒットを狙ってるような振り方をするバッターが多いように感じます。
『果たしてこの場面でそんな大振りする必要があるのか??』と思ってしまうこともしばしば。
【初球打ちはそんなに有効か】
3連戦 2戦目(6/15)の6回の攻撃は見応えありました。
しかしながら5人連続初球打ちでした。
相手のピッチャーが先発でもなくこちらも継投に入っているのでこの場面ではアリだと思いますが、概して横浜のバッターは初球打ちが多いです。
初球打ちは決して悪い事ではないと思います。
何かの記事で見たのですが、むかしむかし、ヤクルトを9年で4度のリーグ優勝に導いた野村監督が1990年にスワローズの監督に就任した時、選手の皆に打者にとって有利なカウントは何か?とひとりひとり聞いて回ったそうです。
多くの選手が0ストライク3ボール、1ストライク3ボールなどと答えましたが野村監督の答えは違ってました。それはズバリ初球だそうです。
ピッチャーは入りからカウントを悪くしたくないという気持ちが働き、初球は無意識にストライクを取りに来ることが多いそうです。よって初球を打ちに行くことは先手必勝の意味でも良い手段の様なんです。
ただ、これはあくまで攻撃上、バッター 対 ピッチャーの1対1の戦いにおけるメリットであり チームとして考えた場合、状況は少し異なると思います。
【いやらしい攻撃、初球打ちのデメリット】
完投能力の高い好投手と対戦する場合、球数を投げさせることが有効な手段の一つであるのですが、初球打ちの場合当然これに該当しなくなるうえ、 皆が初球打ちだと相手の野手は非常にリズムよく守れ相手チームの皆が乗ってしまいます。
相手バッテリーが疲労しないのはもちろんですが 野手も守っている時間が短くなり疲労が軽減され、集中力の低下も軽減されます。自分のところに球が飛んでくるかもしれないとドキドキしながら立って待っている20分と3球で終わってしまう5分では肉体的、メンタル的にどちらの疲労度が高いでしょうか?、どちらが次の自分のバッティングに集中できるでしょうか?
夏場などは特に両者の差が激しいです。
さらに一打席目に初球ストレート打って凡退、2打席目にも初球ストレート凡退で、終盤3打席目のここ一番で打席に入り変化球投げられたら本日の初見となり対応は厳しいものとなるでしょう。
そしてこれが一番大きいのですが味方のバッテリー、野手が、極端な話 攻撃において3人とも初球打ちだったとしたらほとんど休む間もなくまた守備につかなければなりません。夏場の屋外球場でのピッチャーなどは相当な重労働です、肉体的にもメンタル的にも。
以上のような点を踏まえると 初球打ってヒットで出塁するバッターよりも10球粘ってフォアボールをもぎ取り出塁するバッターの方がチームに貢献しています。
野球はそのゲームにおいてたくさん ヒットを打った方のチームが勝つスポーツではありません。 ベイスターズには 何とかノーヒットで1点取る野球を研究して欲しいと思います。今のベイスターズの野球はひたすら ヒット待ちで、「ヒットがたくさん打てたから勝ちました 」「ヒットが少なかったから負けました」といった野球で 試合後の監督のコメントもあと1本が出なかったが非常に多いです 、どんな優秀なバッターでも3割がそこそこ、今季はボールが飛ばないのか分かりませんが最悪 首位打者の打率が2割台になるかもしれないと言われている シーズンです。
そんな中 、決して足の速くないバッターを並べた場合点を取るまでヒットを続けるのは なかなか難儀です。
確かにベイスターズは能力のあるバッターが多いのですが 、でもそろそろヒット待ちの野球から脱却しても良いのではないでしょうか…
もしベイスターズが今のスタイルで勝ち抜きリーグ優勝しようとするなら 昔の巨人のようにFAで3割3分、30本以上のバッターをもっともっと大量に集めなくては無理だと思います。
1998年前後のマシンガン打線の時でさえ、バントこそ少なかれどここ一番での右打ちやエンドランは鮮やかに決まっていました。マシンガン打線がヒットを続け、1・3塁、1・3塁の形を回していくスタイルでした。琢朗さんは常に考えながら打席に入り、初球に絶好球が来てもほとんど見逃していたとのことです。
因みにバント嫌いで有名な権藤監督とはいえ年間犠打数は68です。
野球はそのゲームにおいてたくさん ヒットを打った方のチームが勝つスポーツではありません ベイスターズには 何とかノーヒットで1点取る野球を研究して欲しいと思います。
セカンドゴロの間に1点入り結局これが決勝点……のような試合をもう少し増やさないと常勝は厳しいかと。
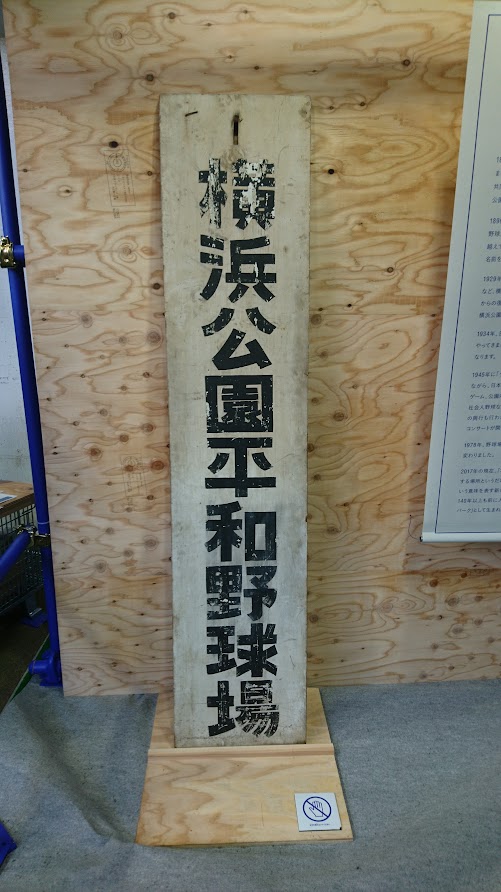


コメント